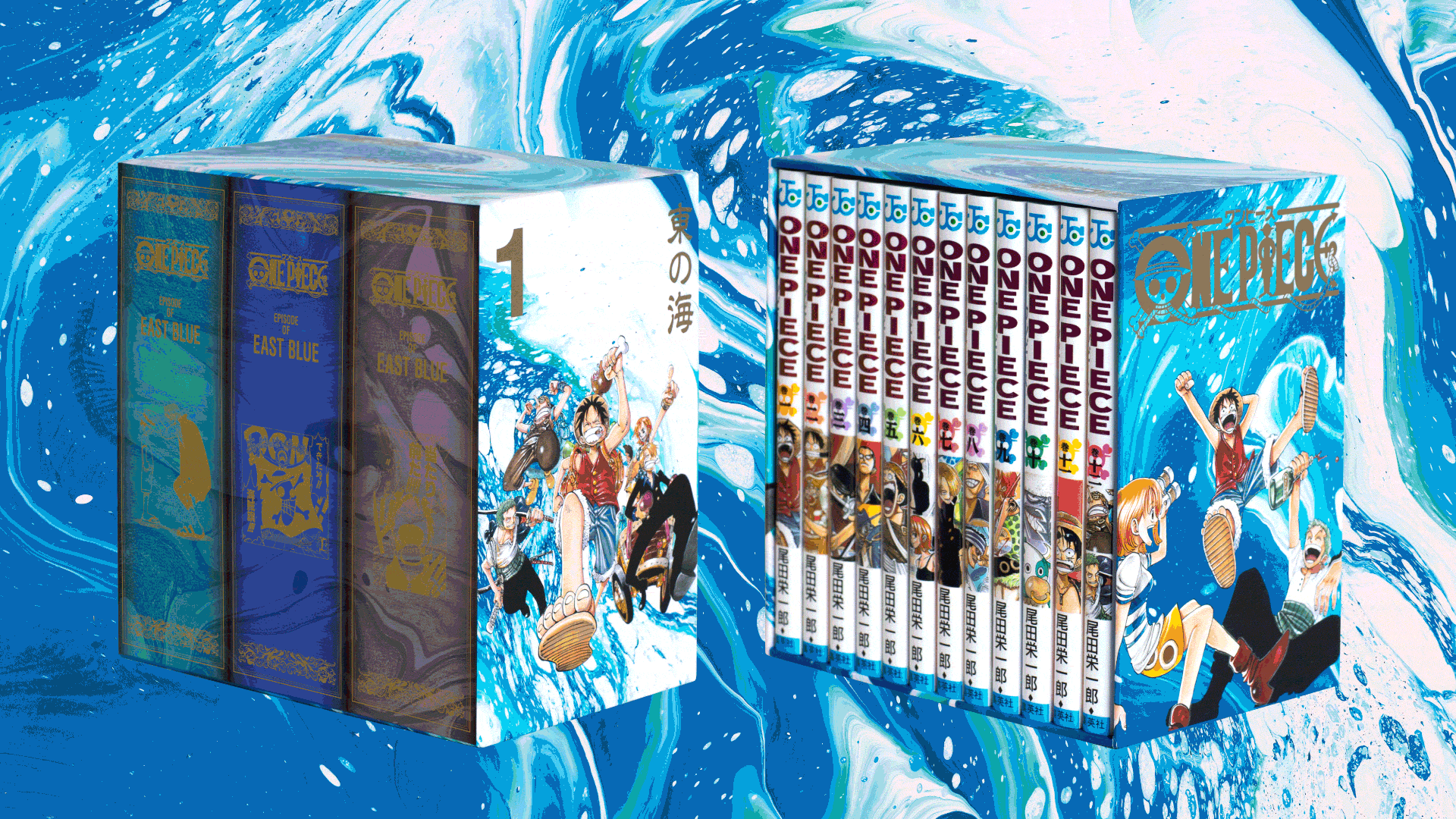『ONE PIECE』デザインワークスの裏側 ― 予告編からボックスデザイン、千話記念ロゴに至る作品愛と解釈。
2021.07.20

Helixes Inc.のメンバーやそのマインドについて発信していく「Helixes.log」。
今回は国民的作品である漫画『ONE PIECE』の仕事に継続的に携わるプロデューサーの平嶋と、アートディレクターの梅田に、「作品愛とクリエイティブ」をテーマに話を聞きました。
「自分たちなりの作品への解釈が、クライアントと違ったらその仕事は受けない」とまで言い切る両者は、いかにして『ONE PIECE』ファンを魅了するクリエイティブを生み出し続けているのでしょうか。
Helixesのクリエイティブチーム・maxillaの強みである「作品を愛するカルチャー」とクリエイティブとの密接な結びつきをひもときます。
『ONE PIECE』を扱うということは、日本国民全員が「対象」
―maxillaと『ONE PIECE』のつながりは東映アニメーションのお仕事から始まったそうですね。
平嶋 「アニメのスペシャル回のYouTube用予告動画を作りたい」とご相談いただいたのが最初の依頼ですね。サンジがメインのエピソードだったので、彼がどんなキャラクターなのか今一度向き合わないとだめだと思って、アニメを800話あたりまで一気に見返したんです。
そうやって作品と深く向き合ったうえで、最新の映像と、過去の映像を切り貼りして「このシーンは使いたい」と東映さんにお話しながら編集を進めました。
クリエイティブ的には、モーションやエフェクトががっつり入るみたいなものではなく、シンプルに本編の映像を組み合わせて作ったものです。ですので、映像制作の技術力というよりは、作品への考え方や思いでプレゼンテーションを行っていった形ですね。
―その後も、ゲームの予告映像やフィギュアの企画、ついには集英社と書籍関連の仕事など、さまざまな角度で『ONE PIECE』に関っています。日本を代表するタイトルとの仕事について、改めて振り返ってみていかがでしょう。
平嶋 ファンの数が多く幅も広いので、『ONE PIECE』を扱うということは「日本国民全員が対象」と言えます。「ターゲット」という表現を使うには、対象が大きすぎる。だから、よくある広告的な「ターゲットの年齢層は◯歳ぐらいだから、こういう演出手法にしましょう」というロジックは通用しないんです。そうしたマーケティング的な観点ではなく「ONE PIECEのファンが魅力を感じるにはどうするか?」 という視点で制作することを徹底的に意識しています。
―詳しく教えてください。
平嶋 例えば、先ほど話した予告映像を担当したスペシャル回では、サンジが仲間のために身を引く展開が描かれていきます。
サンジは、敵対関係にあるビッグ・マムに「娘と結婚して仲間になれば、麦わらの一味を助ける」と迫られます。葛藤しながらも、犠牲になることをいとわない彼は仲間のもとから離れる決意をする。この葛藤や決断に至る過程は、彼の性格を深く知るサンジファンであれば痛いほど分かるんです。
一方のルフィはサンジに「そんなの関係ないから帰ってこい」と、引き止めようとします。ルフィは、サンジの葛藤を感じながらも、彼らしい無邪気なやり方で止めようとするんです。
こうしたエピソードの魅力を伝えるために、サンジとルフィの過去のどの映像がふさわしいか、サンジの本音が出ているシーンはどこか、と考えながら予告映像の中に盛り込みました。ターゲットが誰かというよりは、サンジが好きな人、ルフィが好きな人に向けて「このスペシャル回を観たい!」と思ってもらえるような映像を作ったんです。『ONE PIECE』という作品、そして『ONE PIECE』が大好きな人に徹底的に寄り添う、という考え方ですね。
―エモーショナルな作り方ですね。
平嶋 『ONE PIECE』に関しては、毎回様々な感情に訴える作品をつくろうと意識しています。ただ、今のはエピソードがベースにある作例なので比較的分かりやすいんですけど、『ONE PIECE』の“デザイン”となるとこれまた難しいんですよね。
都度問われる「ONE PIECEらしさとはなにか」
―最近ではコミックスをエピソードごとにセットで収納できるボックスのデザインを担当しましたね。
梅田 ボックスのデザインコンセプトについては、かなりたくさんの方向性を思案しました。提案したいくつかの案から一つを選んでもらうつもりでしたが、お見せしたところ「全部いいので、全部を入れ込んでみてほしい」というご要望をいただき、そのすべてのアイデアを一つに落とし込んだものが、最終形となっています。
―どういったコンセプトなのでしょうか?
梅田 『ONE PIECE』の世界である青い星の「海」をそのまま再現すること、つまり「各巻を並べたときに海がひとつにつながることで、ルフィたちの冒険の舞台と軌跡を視覚化すること」をひとつのコンセプトとしています。各エピソードを構成する要素(舞台となる島、活躍するキャラクター、天候、そこで発生する事件など)を可能な限り抽出または解釈し、波模様として再構築することで、そのコンセプトを最大限に具現化できる、と考えました。
でも、海は常に表情を変え続ける非人為的な存在ですよね。この流動性や偶発性、いわば「自然」を表現するためには、あえて完全には人の手でコントロールし得ない「水」で描くのが必然でした。そこで、水の上にインクを浮かべ、そこに素材を乗せてインクを転写する「ハイドロディップ」という表現に強い「Dirty Workers Studio」というチームにお願いすることにしたんです。微細な色合いの変化の中に、エピソードから抜き出した要素が象徴されています。
また、大きな流れに沿って物語が進んでいることを表現するために、背表紙は波模様がずっとつながっています。実はこの先の発売予定分まで背表紙はすでにできていて、2メートルぐらいの大きな1枚の木に描いてあるんです。全部揃えると、最初の1巻から僕らもまだ見ていない最終巻まで一つの大きな海で、航路としてつながる。これも『ONE PIECE』の世界を、自分たちなりに解釈したうえで設計したデザインです。
平嶋 数あるエピソードの中でも高い人気を誇る、頂上決戦編のボックスのデザインも面白いですよ。頂上決戦編では、地震を起こす能力を持つ白ひげというキャラクターが出てきます。白ひげが能力を使うと津波が起きるのと同様に、ボックスのデザインでも1回波が切れているんです。白ひげ以外にも頂上決戦編にはさまざまなキャラクターが出てくるので、多様な色が混じり合っているのも特徴ですね。

梅田 このボックスのお仕事を尾田先生に気に入っていただけて、画集のデザインのお仕事もご依頼いただいたのですが、このときはなるべく尾田先生の絵の世界観そのままに、余計な装飾をせず、配置や組み方で極力シンプルに見せていくことを考えました。関わってきたプロダクトの種類はさまざまですが、都度「ONE PIECEらしさとは」を問いながらアイデアを練っています。

―これだけのビッグタイトルで、自身も長く接している作品と仕事をするのは感慨深かったのでは。
梅田 そうですね。実は僕、漫画家になりたいと思っていたことがあって。おこがましいんですけど、『ONE PIECE』を読んだときは悔しかったんです。めちゃくちゃ好きでおもしろいけど、素直に好きだと言いたくない(笑)。そんなことがあったからこそ、尾田先生のお仕事が今できていることは、ほんとうに感慨深いですね。
平嶋 僕の感覚としては、変な言い方ですが「ONE PIECEってこんなすばらしい作品なんだ」と映像やデザインを通して勝手に紹介しているイメージです。いまだにずっと読むのが楽しみな気持ちを大事にしながら、現時点で僕が思っている『ONE PIECE』の解釈を詰め込んで表現している感覚。逆に言うと、狙って作ってないんです。計算ではなく、自分なりに考察をして楽しみながら表現している。
当然、僕もこの先の展開を知りません。あるキャラを気に入って、こんなにいいキャラなのだという表現を作ったとしても、後になって実は悪いキャラだった、という可能性だってあります。「自分はあのキャラは悪い奴だと思っていた」と言う人もいると思います。でも、そうした解釈の違いすら、読者同士で楽しんでいるのが『ONE PIECE』という作品の魅力でもあるんですよね。
梅田 それぞれのキャラクターにそれぞれの正義があって、多面的ですからね。それと、これは『ONE PIECE』ファンなら言うまでもないのですが、数字あそびや語呂合わせ、扉絵などにとんでもない伏線が隠されていたりするのも大きな魅力です。僕も未だにYouTubeなどでファンの考察を掘ったりしています。
作品への愛と解釈を曲げないから「maxillaの作品」だと言える
―たとえば『エヴァンゲリオン』のファンが持つ熱量とは、またベクトルが違う感じもしますね。
平嶋 そうですね。ただ、僕らは他の作品を扱うとしても、同じスタンスを貫くと思います。「俺らの●●●●はこうなんだ」というのを、アイデアや作品に詰め込む。仮に、その解釈がクライアントと一致しなかったら、その仕事は多分やらないと思います。僕らは、「自分たちの愛した作品」を裏切りたくないんです。
―そこまで言えることがすばらしいですね。
平嶋 だからもし思い入れのある作品に携わったとして、クライアントが出してきた案が気に入らなかったら、「それはめちゃくちゃダサいですよ」とキッパリ言うと思います。そこはmaxillaのメンバー全員が持っている強みですね。
逆に、ここまで言う覚悟を持っているからこそ、自分たちのクリエイティブに対して適当なことは絶対にできません。もし自分がその作品のファンだとして、誰かに適当なものを出されたら、絶対に嫌ですから。広く世に知られていない作品であっても、その作品を本当に愛する人がクリエイティブを担えば、感情を揺さぶるものが作れると思います。
―仕事だからといって、作品への愛を歪めるようなことはしないと。
平嶋 そうですね。熱量を持って「これが好き」「これをやりたい」と言えるかということが大事です。今回は『ONE PIECE』がテーマですが、作品がマジョリティに評価されているかどうかは関係ありません。世間的な評価は悪くても、自分たちが愛する作品だったら全力を注ぎます。
梅田 作品への愛、という意味で個人的に一番『ONE PIECE』への愛が表現できたと思うのが、1000話を記念したロゴです。ちょうど今エピソードが展開している舞台が「ワノ国」だということで、家紋のようなデザインにしました。無粋になるのでここでは言えませんが、漫画本編とのリンクを感じれたことも嬉しかったですね。
―maxillaには作品愛がある人たちが多いですね。
平嶋 本当にそう思います。自分たちが好きな作品を題材に、映像なり、デザインなりを通して「maxillaとしての作品」を作っている感覚です。好きでもないのに「有名な作品の映像を作りました。すごいでしょう」と発表するような軽い気持ちは誰も持っていない。
maxillaはミュージックビデオなども幅広く作ってきましたが、有名なアーティストもいれば一般的にはまだ認知度が低いアーティストもいます。でもどのミュージックビデオも、自分たちが愛するアーティストを、最高に格好良く撮ったという自信を持って発表しています。
『ONE PIECE』のような作品も、そのファンの人たちに向けて「maxillaが作った」と自信を持って言えるかどうかは大事だと思います。そうした思いで作っているからこそ、アニメの予告映像からスタートして、数珠つなぎ的に本丸である集英社とお仕事をさせていただいているのだと思っています。
何度もお話ししたように、作品に対する愛、そして自分たちなりの解釈は絶対に曲げない。そのうえで、映像やデザインのクオリティでも、他よりも絶対に良いものを作れるという自信があります。これからも、『ONE PIECE』はもちろん、もっと多くの自分たちが愛する作品と関われるように、最高のクリエイティブを生み出し続けていきたいと思っています。
-
Interview & Text
Kentaro Okumura
-
Edit
Luna Goto
Kohei Yagi
Helixesへのお問い合わせはこちら Contact