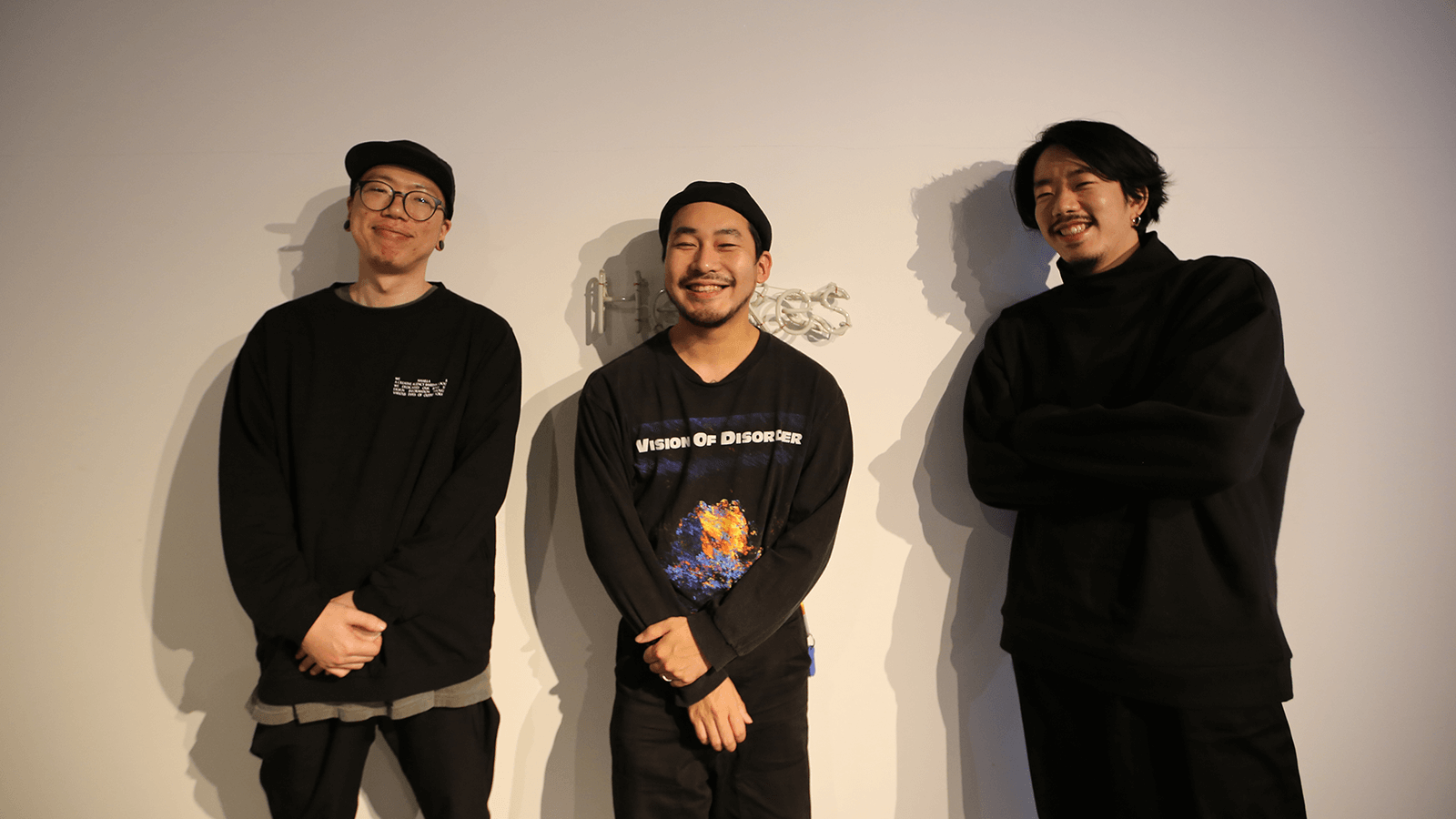企画から製造、販売まで──PJMと生産管理が語る、前例なきモノづくりの面白さ
2025.10.10

Helixes Inc.のメンバーやそのマインドについて発信していく「Helixes.log」。
今回は、PJMの山浦、新津、梶野、高木の4名に集まってもらい、プロジェクトマネージャーという仕事について話を聞きました。映像制作に留まらず、イベント制作や空間設計、EC事業など、年々その領域を拡大しているHelixes。その複雑化するプロジェクトを支えるPJMと生産管理のメンバーが、具体的なプロジェクト事例と共に、制作の裏側から仕事の醍醐味まで、リアルな声をお届けします。
─今回はHelixesのモノづくりを支える皆さんにお集まりいただきました。まずはそれぞれの役割から教えてください。
梶野 私はMEQRIのブランドマネージャーとmaxilla(Helixesのクリエイティブエージェンシー事業部)のプロジェクトマネージャー(以下、PJM)を兼任しています。MEQRIはHelixesの自社事業なので、まず社内で作った企画を漫画やアニメの版元様に提出して許諾をいただくところから始まります。その後、企画が通るとデザインを制作し、工場さんとディテールを詰めて製造するという流れです。私はブランドマネージャーとして、企画から製造進行、リリース、PL管理、対外的なブランディングまで、ブランドに関わるすべてをコントロールする立場です。
高木 私はHelixesに入社する前は撮影スタジオでレタッチャーとして9年ほど働いていましたが、新しい分野の仕事がしたいと思い、2022年7月からHelixesで働き始めました。今はほぼMEQRIの専属として、製造に関わる進行管理を担当しています。梶野さんがMEQRI全体のコントロールをしつつ、私はより現場に近いところで、デザイナーと連携したり、製造業者さんとデザインの実現可能性を検証したり、コスト面の調整といった具体的なやりとりも行っています。



山浦 私は普段プロダクションマネージャー(以下、PM)という役職で映像制作を中心とした制作進行全般を担当しているのですが、今年5月に開催した展覧会「〈物語〉シリーズ × Mika Pikazo POP-UP『ENCOUNTER 遭遇』」ではPJMを担当しました。展示作品の印刷進行からグッズの生産管理、会場の施工や運営まで、かなり幅広く関わらせていただきましたね。
新津 私もmaxillaのPJMとして様々な案件に関わる中で、映像やイベント案件で必要になる空間装飾やノベルティ、アパレル類の生産に関わることがあります。例えば『precure genic(プリキュアジェニック)』では、イベント全体の進行をしつつ、ポップアップ会場で使う小冊子やオリジナルランプ、オブジェを作ったり。全体進行を進める一環としてグッズ制作も担当する、という形です。





前例なきモノづくりの積み重ね
─多岐にわたるモノづくりに携わる中で皆さんが感じている面白さや難しさについて教えてください。
梶野 難しいところは、商品仕様と原価のバランスを設計する部分だと思います。可能な限りクライアント様やお客様に喜んでいただける商品を作りたいけれど、製造にかけられる費用の範囲は決まっています。そこで、商品の素材やデザインを工夫しながら、いかに仕様と原価の良いバランスをとっていけるかが、生産管理の腕の見せどころの一つかなと思います。
楽しいところで言うと、製造業者さんと長期的な絆を形成していけることですね。ただ発注するだけでなく、相互に影響し合いながらモノづくりができるところに、このポジションが存在する価値を感じます。
高木 予算と納期とクオリティのバランスについてはいつも難しいと感じるところです。商品によって材質、印刷手法、質感まで検討していかなければならないですし、専門的な知識がないと工場の方と対等に話せません。そこは日々勉強ですね。
梶野 特にMEQRIは自分たちのブランドだからこそ、絶対に妥協したくないという気持ちが強いんです。コストとクオリティのバランスを考えながら、どうすれば一番良いものが作れるか。そのせめぎ合いは大変だけど、面白い部分でもあります。そのためにもMEQRIチームでは毎朝の定例で進捗を細かく確認して、認識のズレが起きないように意識しています。
新津 私はやったことないものを作るときが楽しいです。あるゲームの世界大会(日本開催)では、クライアントのブースに設置する5m×3mの特大バナーを作りました。ブースの構造や施工に時間をかけられないが効果的な宣伝をしたいという要望がある中で、「めちゃくちゃでかいバナーを設置すればいいんじゃないか」というアイデアが出てきて、「やったことないけど作ってみよう」と。リサーチから始めて試行錯誤しながら作ったところ、すごく迫力のある完成品になりました。仕上がりが良くて、しかもクライアントの要望が叶えられた時はやっぱり嬉しいし、楽しいですね。前述の『precure genic』の時も、アイス屋さんのような大きなアイスのオブジェをオリジナルで塗装までしたり。そういう経験をすると「作れないものってないのかも」と思えてきます。
山浦 私は今回イベントの制作が初めてだったので、施工とか運営、チーム全体の動きはプロデューサーと話し合いながら、本当に手探りで進めていきました。施工会社の人にも「こういう風に考えてるんですけど、実際どうですか?」って聞いたりして。そうやって苦労して進めたのが実際のデザインやモノとして仕上がった形で見ると、すごく楽しいですよね。だから、大変なことがあったとしてもその記憶は薄れて(笑)、いつも最後には「楽しかった〜」と思うことが多いです。


クオリティのための真摯なコミュニケーション
─Helixesの文化だからこそ生まれる面白さややりがいはどんな点がありますか?
梶野 HelixesのPJMは、ただ進行管理をするだけじゃないんです。例えばMEQRIなら、どんな企画にするか、どんなグッズを作るか、という上流の部分から関われる。一般的な制作会社だと分業されていることが多いと思うんですけど、企画から製造、販売まで一気通貫で見られるのはすごく面白いし、やりがいがあるはずです。
新津 案件の企画段階から入ることが多いので、「こういうノベルティがあったら、もっと面白くなるんじゃないか」といった提案がしやすいですね。職種に関係なく、みんなでアイデアを出し合って、良いものを作っていこうというカルチャーがあると思います。みんなで「どうしたらもっと良くなるか?」を常に考えている感じです。
山浦 『ENCOUNTER 遭遇』でも、チーム全員がファンの方がどんな展示だと喜んでくれるのか、どういうグッズを求めているかという視点を持ってプロジェクトを進行していきました。〈物語〉シリーズやMika Pikazoさんのファンであるメンバーも多く、自分の「好き」という熱量をそのまま仕事にぶつけられるのは、Helixesならではの魅力かもしれません。
高木 チームワークもすごく良いですよね。何か困ったことがあったら、すぐに相談できる雰囲気があります。私自身、製造管理は未経験からのスタートだったので、進捗状況を確認しながら進めていける環境がとても心強かったです。
梶野 忌憚なく素直なコミュニケーションを取り合えるのはMEQRIというチームの強みだと思います。仕上がりに納得できなかったり、進行で改善すべき点は、変に相手の顔色を伺うのではなく「これは良くない」とちゃんと言い合える。こうしたチームビルディングはブランドの発足時から常に意識してきました。
知見の共有についても、例えば「この加工ならこの業者さんが強い」といった情報はSlackのチームチャンネルで共有するようにしています。結果的にそれが会社の資産になっていきますし、全員でクオリティを引き上げていこうという意識が強いんです。
チームで作品への愛を形にできる人を
─最後に、今後のキャリアの展望やイメージがあれば教えてください。
梶野 引き続きMEQRIの成長にコミットしながら、オリジナルIPなどMEQRI以外の事業にも携わっていきたいです。ブランドマネージャーとして、事業をスケールさせていく経験を積んでいきたいですね。
高木 今後も様々な商品を作る機会が増えると思いますので、まずはPJMとして全体の進行を先読みするスキルを高めながら、様々な要望に応えられるようになりたいです。
山浦 『ENCOUNTER 遭遇』を通して、PMよりも俯瞰した視点でプロジェクトに関わることができ、PMだけでは得られない楽しさがあると気づきましたし、成長にも繋がっていると思います。まだまだ勉強中ですが、別の案件でもグッズの製作進行や生産管理にアサインいただくことも増えてきているので、今後ともスキルアップしていきたいです。
新津 これからもやったことないことに挑戦し続けたいですね。またこの数年、PJMとして仕事をする中で、社内外問わずさまざまな人たちの間に立ってプロジェクトを進めたり、物事を整理整頓したりすることが得意な自分に気づくことができました。こうしたスキルをかけ合わせて、自分ならではの強みを伸ばしていきたいです。

梶野 Helixesでは今、モノづくりへの挑戦をさらに加速させてくれる仲間を探しています。事業が拡大する中で、生産管理の領域はまだまだ手探りな部分も多いのが正直なところなので、特に生産管理のプロフェッショナルな方に来ていただきたいなと。
私たちの仕事はコンテンツIPを扱っており、チームワークが前提になります。なので、生産管理のスペシャリストでありながらも、コンテンツIPへの知見やリスペクトがあり、チームと連携して仕事を進めることにポジティブな方に来ていただけると、Helixesで非常に活躍できるのかなと思っています。
Helixesの面白さは受託制作に留まらない点です。自社事業の開発にも力を入れているので、事業のスケールのために何が必要かという上流の視点から考え、実行できる。そこが一番のやりがいになると思います。もちろん、それが「売れる」という視点も忘れずに、今まで見たことないようなものを作りたい熱意がある方が来てくれると嬉しいです。
-
Speaker
Momoyo Kajino
Moe Niitsu
Yoko Takagi
Hanako Yamaura -
Interview & Text
Michi Sugawara
Kentaro Okumura
-
Edit
Kohei Yagi
Riko Nakagawa -
Photo
AVO
Helixesへのお問い合わせはこちら Contact